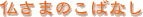|
11 |
スダッタ長者 |
Chijo
|
むかしむかし、インドのコーサラ国に、スダッタという大金持ちが住んでいました。
ある時彼は、隣国でお釈迦さまのお説法を聞いて大変感激し、是非とも自らの国に教団の全員を招くことのできる施設を建て…
|
|
|
12 |
白象の菩薩 |
Kansho
|
お釈迦(しゃか)さまの前世の菩薩(ぼさつ)は、無数の過去世で限りない功徳(くどく)を積んだ結果、兜率天(とそつてん)という天上の世界に昇り、そこで地上に下る時期が来るのを待っていました。 |
|
|
13 |
梵天の懇願 |
Kansho
|
お釈迦(しゃか)さまは菩提樹(ぼだいじゅ)の下で悟(さと)りを開いて七日後のことです。深い瞑想(めいそう)から立ち上がるとアジャパーラ・ニグローダ樹の下に座り、「自分の得た悟りの内容は… |
|
|
14 |
チュッラパンタカ |
Kansho
|
チュッラパンタカ(周利槃特=しゅりはんどく)は、優秀な兄マハーパンタカにくらべ、生れつき愚鈍(ぐどん)で、短い一句の詩も暗記することができませんでした。兄も何とか彼を一人前の修行僧にしてやろうと… |
|
|
15 |
ブッダ最後の説法 |
Kansho
|
病身のブッダは、クシナーラのサーラ樹の下に身を横たえ「弟子たちに教訓を与えずして入滅することはできない」とお考えになられました。意志の力によって病痛を沈められたブッダは、ブッダの入滅が近くなったことを… |
|
|
16 |
多聞第一のアーナンダ |
Kansho
|
ブッダの滅後、出家在家の弟子たちは、ブッダが様々な人々に説かれた教えをまとめ、それを「仏説」として確定するための集会を開きました。これを「結集(けつじゅう)」といい、全部で四回行われたと伝えられます。 |
|
|
17 |
功徳を積む |
Kansho
|
ブッダの十大弟子の一人のアヌルダは、ブッダの法座で居眠りをしたことを恥じて、絶対に眠らないと誓いました。そして厳しい修行を続けた結果、ついに失明してしまいまったのです。 |
|
|
18 |
スブーティ |
Kansho
|
ある日、お釈迦(しゃか)さまの十大弟子の一人スブーティ(須菩提=しゅぼだい)は、お説法のためマガダ国の王舎城(おうしゃじょう)に呼ばれました。そして彼の説法を聞いたビンビサーラ王は大いに感激し… |
|
|
19 |
カッサバ三兄弟 |
Kansho
|
マガダ国のウルヴェーラ地方では、ウルヴェーラ・カッサパという百二十歳を越える火の行者が、大きな勢力を誇っていました。そして彼にはナディーとガヤーという二人の弟がおり、彼らにはそれぞれ… |
|
|
20 |
ソーナ・コーリヴィーサ |
Kansho
|
ソーナ・コーリヴィーサは長者の子として生まれ、生まれてこの方一度も外を歩いたことがありませんでした。そのため足の裏に毛が生えており、それが有名になってビンビサーラ王の耳にまで聞こえたほどでした。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
糞掃衣を着たカッサバ |
Kansho
|
ブッダの弟子のマハー(偉大なる)・カッサパは、衣食住についての貪(むさぼ)りや、頭陀行(ずだぎょう)という執着を払う修行にかけては右出る者がなかったので、「頭陀第一」といわれていました。 |
|
|
22 |
ハトの重さ、ヒトの重さ |
Kouryu
|
ある日、修行僧の衣のたもとに一羽の鳩(ハト)が飛び込んで「どうか私をかくまって下さい」と頼みました。間もなくして、今度はそれを追っていた鷹(タカ)がやってきて、鳩を出してもらうよう修行僧に言いました。 |
|
|
23 |
ドロのだんご |
Shouden
|
お釈迦さまがインドの国中を托鉢(たくはつ)をして歩いておられた時のこと、遠くでドロ遊びをしていた二人の子供が、お釈迦さまのもとへかけよって来ました。そして一生懸命つくった形の良いドロのおだんごを… |
|
|
24 |
欲張りなメス鳥 |
Houjun |
ある日、一羽の欲張りなメス鳥が群れから離れ、人の住む町へ食べ物を探しに行くと、道に米や豆などがたくさん落ちているのを見つけました。メス鳥は目を輝かせてそれをついばみ満腹になると、こんなことを考えついたのです。 |
|
|
|
25 |
お妃の病気と正しい道 |
Ryusho |
昔々、ある国のお妃(きさき)さまが重い病気にかかりました。そこで病気がなかなか治らないのを心配した王さまは、国中の偉い祈祷師(きとうし)を呼んで治療法を尋ねたのです。すると祈祷師たちはこう告げました。 |
|
|
|
26 |
モッガラーナの供養 |
Chijo |
ある日のことモッガラーナは、亡くなった母親が餓鬼(がき)の世界へ堕(お)ちて、空腹に苦しんでいるのを知りました。さっそく神通力を使って食べ物を送るのですがすぐに燃えてしまい、火を消そうと水を降らせても… |
|
|
|
27 |
欲望の虚しさ |
Shouden |
マカダ国の都に、天性の美しさのため町中の男たちから慕われ、彼女と一夜を過ごすためには千金を必要としたシリマーという名の遊女がいました。
彼女は縁あってお釈迦さまに…
|
|
|
|
28 |
ライオンの毛皮 |
Houjun |
ある麦畑に、頭はライオンで背丈や尾はロバに似た奇妙な動物がやってきました。実はある商人が自分のロバに良い麦を存分に食べさせようと、ライオンの頭のついた毛皮をかぶせていたのです。案の定、農夫たちは… |
|
|
|
29 |
鬼子母神の前世 |
Shume |
昔々ある街で、人々が歌い踊ってお祝いしていると、瓶(かめ)を持った一人の女性が通りかかりました。
「さあ、一緒に踊りましょうよ」
あまりに楽しそうなので…
|
|
|
|
30 |
努力の神様 |
Taijo |
丸い頭巾(ずきん)をかぶって右手に小槌(こづち)、左手に袋を担(にな)い、二つの俵(たわら)の上に立つ笑顔の大黒様は、元をたどるとインドの神様です。
仏法を護り、飯食(はんじき)ゆたかに…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
ことの発端 |
Bunkyo
|
ある森を、一人のずる賢く残忍な男が歩いてました。そして、木の枝に白く美しい鳥が羽を休めているのを見つけると、そくざに弓を引いて射止めてしまったのです。
するとそこにもう一人…
|
|
|
|
32 |
スメーダの善行 |
Eishu |
昔あるところに、スメーダというたいそう金持ちの青年がいました。しかし彼は「お金は死んだらあの世へ持っていけない。私はあの世まで持っていけるものを手に入れたい」と考え、全財産を手放し家を出てしまったのです。 |
|
|
|
33 |
貪 欲 |
Yusho |
その昔、ある商人の家に生まれた隊商の長(おさ)が、たくさんの商人たちと旅に出た時のこと。
難路を行く途中、一行は枯れた古井戸を見つけ、水を飲むために掘り始めると…
|
|
|
|
34 |
故郷での説法 |
Chijo |
お釈迦さまが王子としての地位を捨てて出家し、修行の末に悟りを得られてから、どれほどの年月が経った頃でしょうか。噂を聞きつけた父の浄飯王(じょうぼんのう)は、故郷へ帰って説法するよう、竹林精舎におられた… |
|
|
|
35 |
足の不自由な猿 |
Bunsho |
ある山に何百匹もの猿が住んでおり、その中に一匹だけ生まれつき足の不自由な猿がいました。そして何をするにも一歩遅れるため、仲間からはいつも「足手まといだ」と怒られていたのです。それでもこの猿は… |
|
|
|
36 |
貧女の一灯 |
Chijo |
昔々インドのある町へ、お釈迦さまがお説法に来られることになりました。そこで町の人々は、お釈迦さまの徳を讃(たた)えるために、我も我もと油を買い求め、競って大きな火を灯(とも)しました。
|
|
|
|
37 |
鹿野苑の鹿 |
Shouki |
昔々インドのハラナイ国に、鹿のアクシス王が率いる鹿たちが平和に暮らしていました。
ところがある時、人間の国王の命令で鹿狩りが始まったのです。そこでアクシス王は、このままでは…
|
|
|
|
38 |
デーバダッタ |
Chijo |
戒律を厳しく守り、優秀で統率力もあったデーバダッタ(提婆達多=だいばだった)は、お釈迦さまの弟子であり従兄弟でもありました。
ある日彼は、お説法を終えたお釈迦さまの前に進み出て、こう申し述べたのです。
|
|
|
|
39 |
運命的な出会い |
Chijo |
シャーリプトラ(舎利弗=しゃりほつ)と親友のモッガラーナ(目連=もくれん)の心は、いまだ満たされないでいました。二人はインドでも名高い思想家に弟子入りし、師と同等の論客にまで成長したにもかかわらず… |
|
|
|
40 |
四つの門 |
Chijo |
昔々、インドの釈迦族(しゃかぞく)の王子として生まれたシッダルタ太子は、ものごとを深く思い悩む性格からか、あまり体が丈夫ではありませんでした。
父王はそんな息子を慈(いつく)しんで…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
花まつり |
Gentai
|
今から三千年ほど昔の四月八日、カピラ国のシュッドーダナ王のお妃であるマーヤー夫人は、ルンビニー園で不思議な王子をお生みになりました。
王子はお生まれになるとすぐ東西南北に…
|
|
|
|
42 |
月に昇ったウサギ |
Eishu |
昔、インドに仲の良いウサギとキツネとサルがいて、こんな話し合いをしていました。
「私たちは、前世の行いが悪かったためこんな獣(けもの)の姿になっているのだ。今からでも善根(ぜんこん)を施して…
|
|
|
|
43 |
消えた白象 |
Kouryu |
王様の自慢はまっ白な象。王様がその白象に乗って街の中を歩くと、街の人々は口々にその姿をほめ称えました。しかし、みんな象のことはほめても、王様をほめる者は一人もいなかったのです。
|
|
|
|
44 |
布袋さん |
Shouden |
七福神の一人に数えられる布袋(ほてい)さんは、もともと中国の宋(そう)の時代に実在した和尚さんでした。その生き方は天衣無縫(てんいむほう)、いつも大きな杖に大きな袋をさげて町をぶらついていたといいます。 |
|
|
|
45 |
ブタ王とトラ王 |
Shouki |
あるところに、悪知恵を持って大勢のブタたちを束ねているブタ王がおり、そこは皆が常にまわりを蹴落とすことばかり考えている社会でした。
ある時、食料を食べつくしたブタたちは…
|
|
|
|
46 |
星占い |
Yusho |
ある都会の家族が、田舎から嫁を迎えることになりました。そして嫁を迎えに行く当日、突然この日取りについて親友の修行者に星占いを頼んだのです。
しかし、占う前に段取りをしていたことに…
|
|
|
|
47 |
出家した農夫 |
Seigen |
その昔、ある農村に一人の農夫がいました。彼は畑を耕して野菜を作って生計を立てていました。
ある日、彼は思い立って出家し、修行僧となりました。しかし、あまりの大変さに…
|
|
|
|
48 |
蛙の裁き |
Shinjo |
昔々のこと、川に住む毒蛇が魚を追いかけ、誤って人間の網にかかってしまいました。そうして身動きが取れなくなった姿を見るや、魚たちはいっせいに蛇に襲いかかったのです。
体中かみつかれ弱り果てた蛇は…
|
|
|
|
49 |
盲目と象 |
Ikkan |
お釈迦さまのお弟子の一人が托鉢(たくはつ)に出ようとした時、お釈迦さまに呼び止められ「町に行って何か尋ねられても、教えのことだけ話してきなさい」と言われました。そして、こんな話をされたのです。 |
|
|
|
50 |
愚かな男と牛 |
Ryusei |
ある村に、一人の愚かな男が住んでいました。彼は大勢の客人を自宅に招待する機会があったので、自分が飼育している牛の乳をしぼって皆に振る舞おうと思いつきました。
しかし、その招待会は一ヶ月も先の…
|
|
|
|
|
|
|
|
|