 |
 |
||||
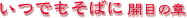 |
|||||
 |
|||||
|
|
一般的に、日蓮聖人といえば「鎌倉時代に活躍した日蓮宗の開祖」と表現されます。ところが以前にもお話した通り、聖人がより所とされた法華経、あるいは聖人ご自身がしたためられた書状等を注意深く拝読すると「日蓮は何(いず)れの宗の元祖にもあらず、また末葉(まつよう)にもあらず」とあります。日蓮聖人は、ただ単に「鎌倉時代に活躍した日蓮宗の開祖」におさまる方ではないのです。
法華経に限らず、八万法蔵(はちまんほうぞう)といわれるほど数多いどの経典も、お釈迦さまがお説きになったものです。 ところが、法華経以外の経典は「その時・その場限り」の教えで、法華経にだけこの教えが「いつ・どこで・誰が・何をもって・どのように」人々を救済するかが説き明かされています。つまり「お釈迦さまが亡き後・末法といわれる時に・娑婆世界(しゃばせかい)・日本に・永遠の命を持つ仏さまが・最高の弟子=上行菩薩(じょうぎょうぼさつ)を遣(つか)わし・妙法蓮華経のお題目をもって・法難迫害を忍受(にんじゅ)し」人々を救済すると示されています。この上行菩薩こそ、日蓮聖人に他なりません。 確かに経文には「上行菩薩=日蓮聖人」とは明記されておりません。しかし法華経全二十八章、なかんずく第十章「法師品(ほっしほん)」から第二十二章「嘱累品(ぞくるいほん)」までを注意深く拝読し、その経説と聖人のご生涯とを重ね合わせていくと「なるほど日蓮聖人は法華経に説かれた方で、他宗の祖師とは似るべくも無く、一宗一派の開祖におさまる方では無い」と理解・納得することができるでしょう。 |

 小坊主のつぶやき
小坊主のつぶやき いつそば「開目の章」
いつそば「開目の章」
 「観心の章」第12回
「観心の章」第12回