 |
 |
||||
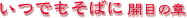 |
|||||
 |
|||||
|
|
立教開宗のその日から、身延山に入山されるまでの日蓮聖人は「二十余所をわれ(追われ)、結句流罪に及び」という状況であり、法門談義あるいは門弟育成もままならぬ状況でした。それ故、身延山では精力的に教義書を述作され、門弟育成に勤(いそ)しまれたのです。「昼は終日(ひねもす)に一乗妙典の御法を論談し、夜は竟夜(よもすがら)要文誦持の声のみす」との一文は正に大聖人の姿を彷彿(ほうふつ)とさせ、現在伝えられるご遺文の大半が身延山で執筆されたことでも、そのお姿をうかがい知ることができます。
そして、古来より伝えられる「立正安国にはじまり立正安国に終わる」との言葉は、日蓮聖人のご生涯を一言で言い表していると言えるでしょう。それは『立正安国論』に示した思想・行動が大聖人の一生涯をかけての願業を標榜(ひょうぼう)したものであり、文応元年七月に時の権力者であった北条時頼に同書を上奏することで、公的布教の開始ととらえることができるからです。 数多くしたためられたご遺文の中で「立正安国論の如し」「立正安国論に勘(かんが)えたる」等の表現は三十数箇所に及び、さらには上奏後も同書を書写されています。これらのことから、大聖人ご自身が同書をいかに大切にされていたかが理解できます。 また最後のご講義はご入滅の半月前、弘安五年九月二十五日のことで、『立正安国論』のご講義であったと伝えられています。 |

 小坊主のつぶやき
小坊主のつぶやき いつそば「開目の章」
いつそば「開目の章」
 「観心の章」第31回
「観心の章」第31回