 |
 |
||||
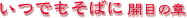 |
|||||
 |
|||||
|
|
法華経の行者とは、法華経の教えに従い、法華経の指し示す通りに修行し実践する人のことをいいます。
日蓮聖人は「法華経の行者漢土(かんど)に一人、日本に一人、已上(いじょう)二人。釈尊を加へ奉りて已上三人なり」と述べられ、さらに「小失なくとも大難に度々値ふ人」が「滅後(釈尊亡き後)の法華経の行者」の資格を有していると示されました。 すなわち、法華経を説かれ九横(くおう)の大難(釈尊及びその弟子たちが衆生を教化する際に起こった、種々の妨害や困難の九種)に値われた釈尊。滅後の像法時代に釈尊と法華経の精神を正しく継承し弘通した天台大師と伝教大師。以上三師を挙げられたのです。 さらに日蓮聖人は、法を広める中で必然的に難に値うことが法華経色読(身に読む)を意味し、法華経の行者としての真実性を表すとされました。 大聖人は「大事の難四度なり。二度はしばらくをく、王難すでに二度にをよぶ。今度はすでに我が身命に及ぶ」と天台・伝教の両師に増した法難を経験され、「日蓮が法華経の智解(ちげ)は天台・伝教には千万が一分も及ぶ事なけれども、難を忍び慈悲のすぐれたる事はをそれをもいだきぬべし」と述べられています。 そして「日蓮は日本第一の法華経の行者なる事あえて疑ひなし」と、ご自身が末法における法華経の行者たる確信を表明されました。 |

 小坊主のつぶやき
小坊主のつぶやき いつそば「開目の章」
いつそば「開目の章」
 「観心の章」第24回
「観心の章」第24回