 |
 |
||||
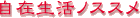 |
|||||
 |
|||||
|
|
「この前、通りがかりの人に因縁をつけられてねぇ」 「大変でしたね。それはまた因縁めいた話ですな」 これは、とある居酒屋での中年男性の会話です。「因縁」という言葉が二度出てきましたね。皆さんも多かれ少なかれ、この言葉を耳にしたり、また実際に使われたことがあるのではないでしょうか。 因縁とは仏教用語であり、広い意味では「ものごとの原因」と説明することができますが、さらに因縁を「因」と「縁」に分け、因を直接原因、縁を間接原因または条件とする見方があります。 例えば、ひまわりの花が咲くための因は種であり、種がないことには発芽して開花することもあり得ません。また、種さえあれば花が咲くかといえば決してそうではなく、水や日光や適当な温度という縁がなければ、美しいひまわりの花を見ることはできません。このような原因と条件を合わせて、因縁というわけです。 さて、よく考えてみて下さい。様々なものごとを結果ととらえ、その原因が何なのかを……。 試験に落ちたのは、自分の勉強不足が原因。交通事故にあったのは、自分の不注意が原因。二日酔いになったのは、前の晩に飲み過ぎたのが原因。けんかになったのは、あの一言が原因。自分がいま生きているのは、父母と生活に必要な環境のおかげ等、挙げればきりがありません。これらはすべて、物ごとの原因である因と縁が複雑にからみ合って起こる結果といえます。そして原因と結果のことを「因果」といい、物ごとの結果は決して偶然ではなく、必然的に起こるということなのです。 何か不幸なことが身の回りに起こったりすると、よく「これは何かの因縁や」とおっしゃる人がいます。例えば、病気になったのは自分の乱れた食生活が原因であるのに、何かの因縁だといっては他のせいにしてしまう場合です。これでは、冒頭での中年男性の会話に出てきた「通りがかりの人につけられた因縁」と同等で、言いがかりにしかすぎません。単なる「都合のいい因縁」になってしまい、因縁めいた話にさえなりえないでしょう。 何もかも自分に都合良く考えたり、他人や環境のせいにしてしまっては、反省や向上心を失い、この先の人間的成長など期待できません。結果だけにとらわれず、なぜそうなったのかという原因をしっかり見すえること。さらに今の結果がどうあれ、それを良い結果へと転じるには、今どのように行動をしていくかが大切だと思うのです。 |

 小坊主のつぶやき
小坊主のつぶやき 自在生活ノススメ
自在生活ノススメ