 |
 |
||||
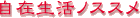 |
|||||
 |
|||||
|
|
ボランティアについて書くはずが、人の心の働きの複雑さについてばかり書いてきた。つまりは前置きが長くなってしまったということである。
なぜか?ボランティア活動は立派なこととされているので、その欠点をあげつらうと過剰反応をひき起こしかねないからだ。だからついつい言い訳がましくなってしまう。もっともこれから書く欠点に過剰反応する人は、まさに痛いところを突かれたからだろう。 援助を受ける側の「甘え」がよく指摘される。阪神大震災の時にも、問題になっていた通りだ。つらい状況下ではついつい目の前にいる人に頼ってしまう、というのは無理からぬことと同情申し上げる。また老人介護施設などで、慰問を受けたあとの老人たちの変化についても、いたし方のないところもあろう。 しかし、こうした「甘え」をできるだけ防ぐための方策も、探っていかなければならない。でないと「仏作って魂入れず」になりかねないからだ。気の毒な状況におちいった人たちを、さらに気の毒な状況に追いやることは避けなければならない。程度によるが、自浄機能を失ったり、自助努力を放棄してしまうことは、決して望ましい状態ではないのだ。 一方で、援助する側にも問題がないわけではない。以前こんなことがあった。三〜四十人ほどの集まりでのこと、ある人が若いころのボランティア活動の経験を語っていたところ、聴いていた者ほとんどがいやな気持ちになり、しらけてしまったのだ。 また別の話もある。ある女性が視覚障害者のために、本の朗読したり、それを録音する活動に参加したところ、他のボランティアの人の障害者に対する理不尽な扱いや、リーダーシップ争いに嫌気がさし、二〜三ヶ月でやめてしまったのだ。 これらには色々な原因が考えられるし、またそれらの総合で起きる問題でもあるのだろうが、中でも最も気づきにくいことを一つだけあげておこう。それは「立場の弱い者を援助することによって、自らの立場の強さを確認し、幸せに浸る」というものだ。これを意識できれば、排除することも可能であるが、意識できていない場合、援助される側の人たちにもこれが無意識のうちに伝わり、決して喜べない。「見返りを求めない」と言いながら、本人が気づかない内に「見返りを手に入れて」しまっていることになりかねないのだ。 前の女性の場合には、事前に愚僧が忠告していたこともあって、自身の心については十分に注意していた。そのかいあって障害者の方たちには喜んでいただいていたようだが、やはり難しい問題だ。ひょっとしたら「甘え」の問題も、援助する側がひき起こしているのかもしれない。つくづく「布施(ふせ)」の精神をかみしめなければならないところだろう。〈おわり〉 |

 小坊主のつぶやき
小坊主のつぶやき 自在生活ノススメ
自在生活ノススメ